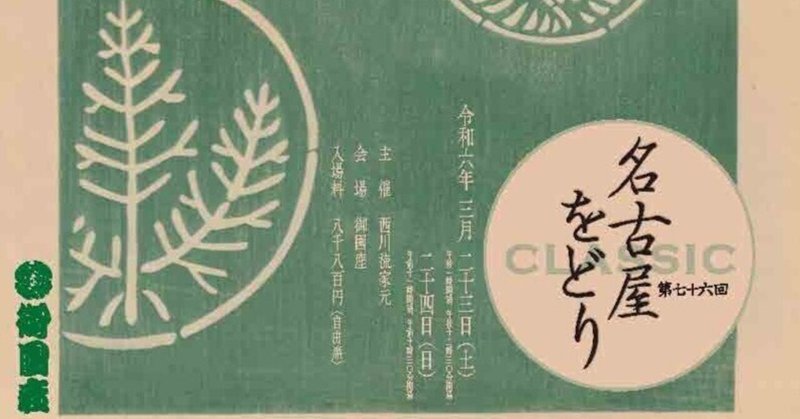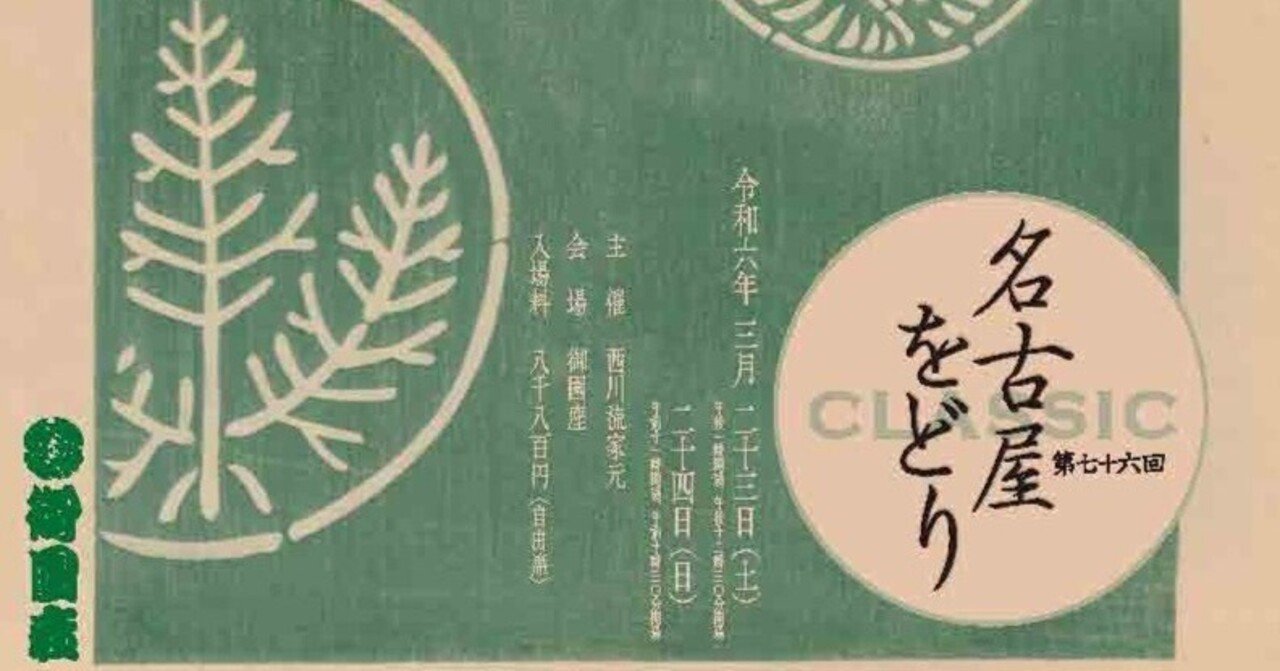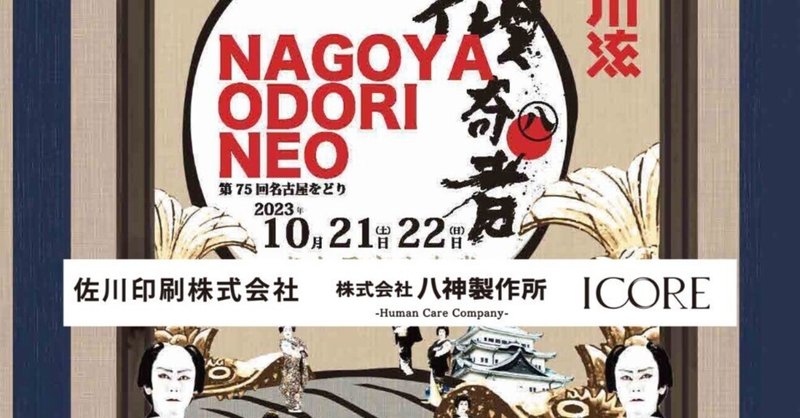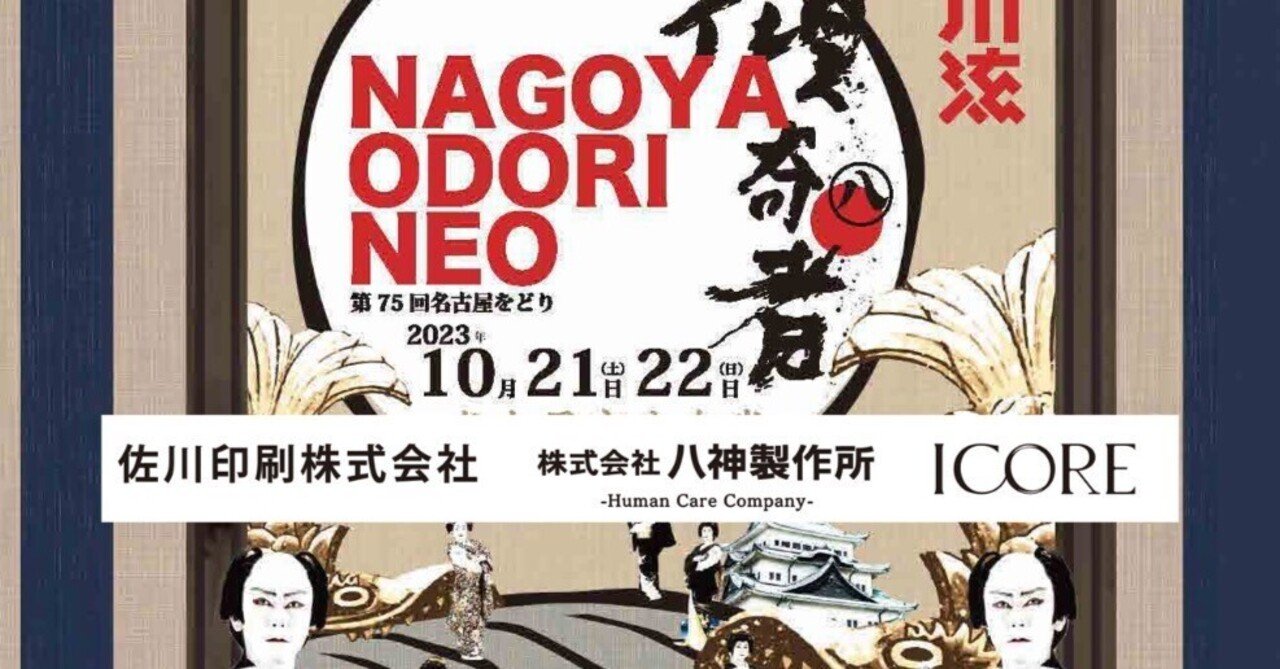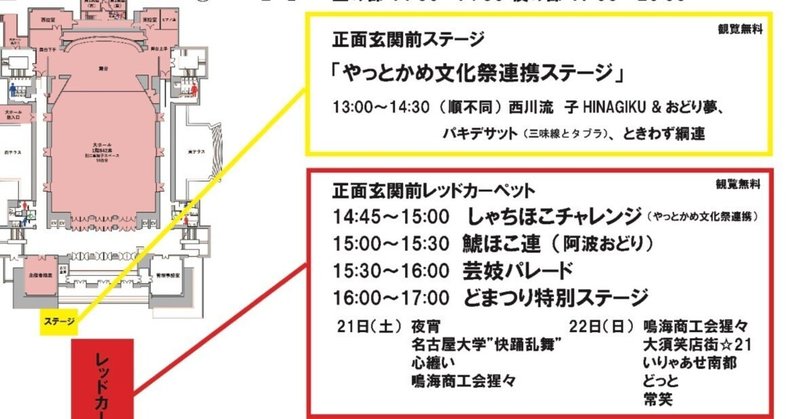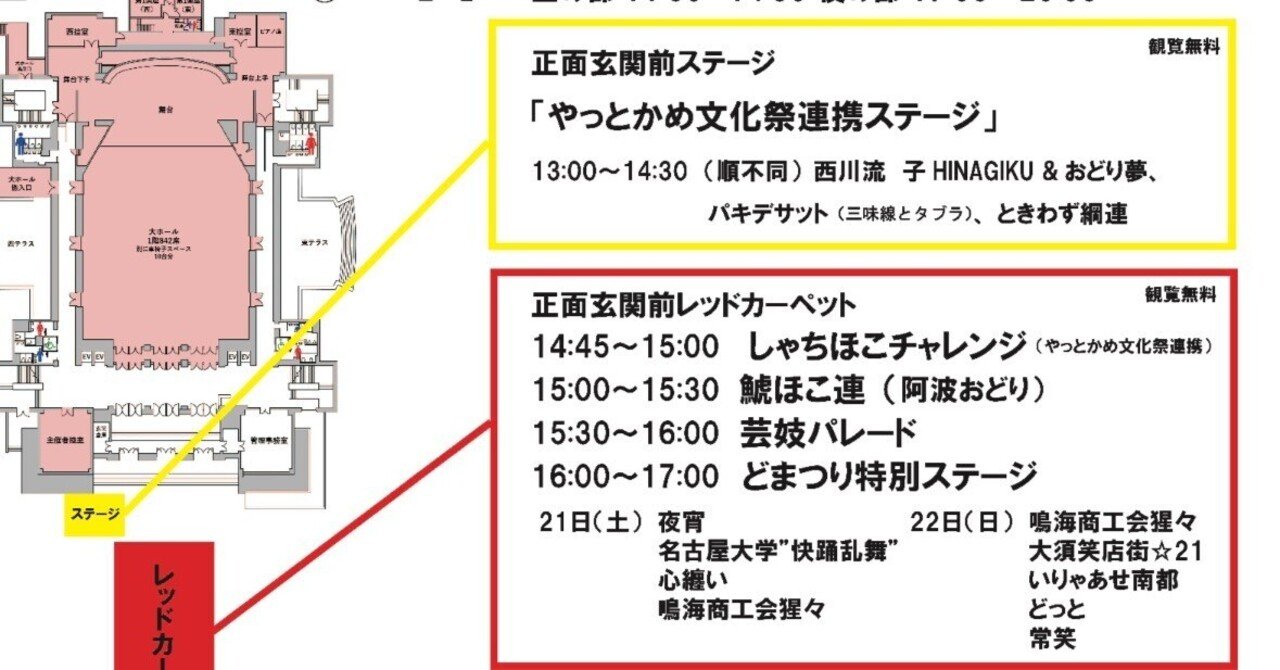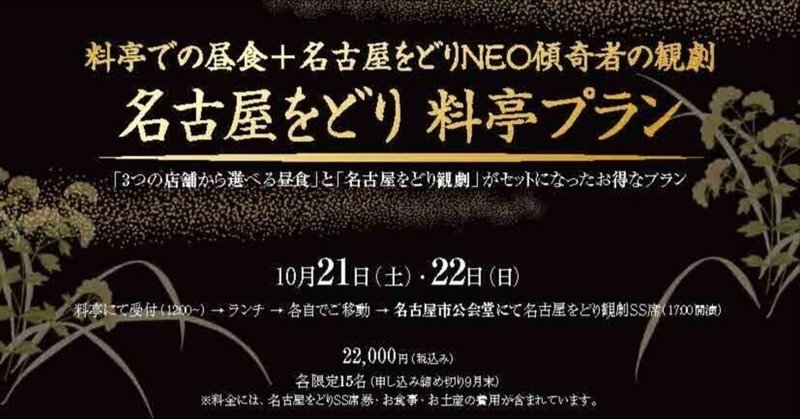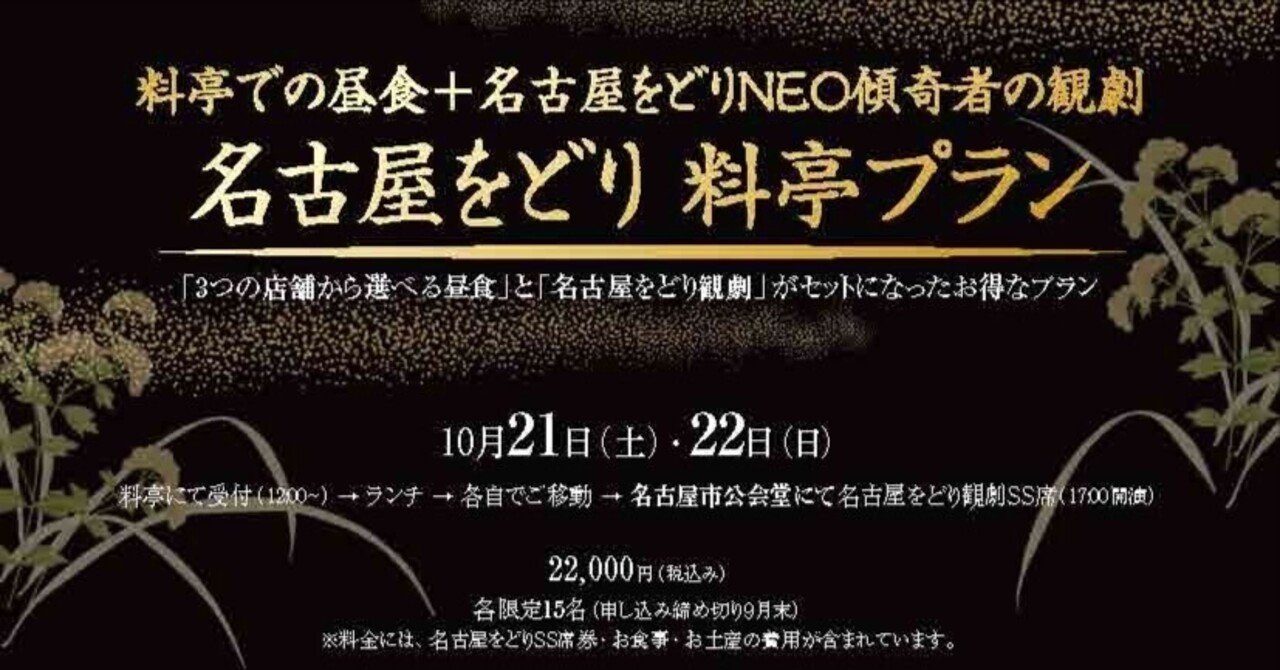最近の記事
- 固定された記事

眠っている振り袖を着て、御園座に立ちませんか?(そして少し踊ってみる)〜清女舞(きよめまい)名古屋をどりCLASSIC 2024/3/23,24御園座
“私が御園座に立つ?”異例の企画がスタート。 「清女舞」(きよめまい)とは…、 名古屋をどりCLASSICで発表される新たな一般参加。 振り袖はその名の通り「袖を振る」ことに由来し、長い袖が特徴で、日本では古くから“振る”しぐさには厄を払う、清めるなどの意味があります。「清女舞」は、長い振り袖を振りながら踊る新しい踊りです。大勢で、御園座の舞台で踊ると言う貴重な体験をしていただきます。 歌舞伎からミュージカルまで、あの舞台に立つ、ということ。 舞台に立つ、というの体験は
- 固定された記事